1990年代後半に開発されて、当時の老兵の想像と全く違う使われ方をしているのが二次元コード(QRコード)である。
この二次元コードだが、その昔PC関連の雑誌には毎月常連の様に掲載されていた時期がある。
当時はまだ「デンソーウェーブ」では無く「デンソー」の名前で出稿されていて、当時の老兵の感想は「なんだか凄い技術だけど何に使うんだ?」という感想でしか無かった。
自動車業界ではバーコードだと全く情報が足りず品質管理には別のものが必要だったことを知ったのは、もっと後年のことだ。
2000年前後、アパレル関連向けにハンディースキャナーのプログラムをしていた事があった。
在庫管理や棚卸に使うのだが、例えば倉庫なんかでどこに置いたか分からない商品を、適当にバーコードを当てると振動や音で教えてくれるようなプログラムである。
売れ残りの季節商品なんかは倉庫の奥に眠っておりセール品として放出するのだが、商品が出ないので誰も覚えていないのである。
商品販売用のバーコード(JANCODE)は、80年代のコンビニエンスストアーの出店増加と共に一気に普及したのだが、バーコードにはいくつかの規格がある。
JANCODEは、13桁または8桁の数字のみで構成され規格化されている。一番よく見る物だろう。

他によく見かけるのは、宅配便で使われている「NW7」だろうか。
これは数字に加えてアルファベット(A,B,C,D),記号(-$/.+)が使えるものだ。
スタート/ストップキャラクタというものが定義されており、宅配便においては通常最初と最初がaのコードのものである。よく見るとJANCODEとは違うのが分かる。
実は「NW7」には桁数に制限がない。やろうと思えば100桁のコードも作れるけど、実質的に端末側で読めないのだ。20桁くらい迄なら適当な距離で読めるけど、それより長いと位置合わせが難しく、合っていても距離が遠すぎて白黒の判別が難しい感じ。全く実用的ではない。

それ以上となると「CODE39」という規格を使用することが多かった。数字、アルファベット大文字、記号(-.$/+%スペース)を使用することができるので、意味を持たせることができ桁を圧縮できるのだ。
スタート/ストップキャラクタに「*」記号を使っているもので、最初と最初が「*」になっている。こちらは工場などでよく使われている。PCパーツでも見かけるし、お酒のボトルなんかでもたまに見るね。
ちなみに「CODE38」というものもあるが、こちらは酒業界では有名なソムリエナイフのブランドで全くカテゴリーが違います。。。
アパレル業界では「CODE39」をよく見かけた。コードに色々と意味を持たせて下段にある英数字を見れば意味が分かるようにしていた。
こちらも桁数に制限は無いのだが長いとやっぱり扱いにくいので、上下2段バーコードにする会社もあった。
当時開発していた経験からすると、2段にすると上下で2回読まなければならず、面倒だった。それに合わせた専用のハンディースキャナーのプログラムを組んでいたのだが、適切な順番に読まないと他の製品のバーコードと混同してしまうのが難点だった。
もちろん、これを回避するための色々工夫もしたのだが、面倒な事に変わりは無い。
今思えば「二次元コード」を使えば瞬く間に解決できただろう。
話を雑誌の広告に戻すと、おかげで「二次元コード」というものの存在は知ったのだが、全く製品を見かけたことはなかったし、このようなことに解決する規格だとは全く知らなかった。
当時のデンソー社も「二次元コード」というものを開発したけども、製品管理以外に何に使えるんだ?という状態だった様に思う。当時はまだ特許は降りておらず「特許出願中」だった記憶がある。
ちなみに広告においての「特許出願中」はアピールの意味しか無い。実運用的にはその後、出願審査請求、出願公開、審査結果などを得て、やっと特許が認められる感じだ。
他社への牽制のために「特許出願」だけしておいて、意図的に審査請求を行わないこともあるし、そもそも特許として認められないこともある。拒絶査定となるなら曖昧な方がメリットがあったりする。
後から類似特許が申請された場合に、先行技術として主張できたりするので、とりあえず出願だけしておく会社も多い。
「二次元コード」の広告にはデカデカと「FAXでデータが送れます」という標語が載っていた。
QRコードの仕様として確かに英数字記号に加えて漢字も扱えた。これは日本産として大きなメリットだろう。
ただ個人的にデータを二次元コードにして、FAXで送る意味が全く理解ができなかった。通信モデムは既に実用的で、企業においてはISDNも普及していた。
わざわざ二次元コードへ変換して印刷して送るより、そのままデータとして送る方が高速で手軽だ。
FAXで送る場合ハフマン圧縮というアルゴリズムを応用しているのだが、横一列が全部真っ白だと最も圧縮率が高い様にできている。紙に何もデータが無い(真っ白)状態だ。
基本的に白または黒だけのデータが続くと圧縮率が高いのだが、白黒白黒・・・と細かく連続してしまうと、ほとんど圧縮されない。二次元コードがまさにその状態なので、送信時間も相当かかるはずで全く意味が分からなかった。これについては今でも同じであろう。
そのためか、しばらくすると広告を見ることは無くなった。
それと同時に二次元コードの存在を20年近くも忘れていた。。。
(そんな訳で記憶には残っているが資料が全く無い。もしかしたら誤情報もあるかも)
二次元コード(QRコード)が一般に認知されたのは、中国においてQRコード決済が普及したニュースを見たときだろう。
自分もこのニュースを見て当時を思い出して色々と調べた。あれから特許権を取得したものの権利行使せず無償で公開されていることに驚いたものだ。
当初は「中国のQRコード決済は偽札が多いため普及したけど、日本には当たらない。本命のFelicaもあるし」との声が多数だったが、今では当たり前に普及した。
それどころか、あらゆるチケットなんかも二次元コードによるチェックが一般的になった。もはや無いと生活に困るレベルである。
- 携帯電話(スマートフォン)にカメラは標準搭載となった。
- モバイル端末からインターネットへの接続も常時可能になった。
- フィーチャーフォンに比べて大画面で、処理速度も大幅に上がった。
ということが大きいだろう。
30年前のハンディースキャナーは「KB単位」のメモリーしか搭載されておらず、しかも低性能なモバイル用CPUを使用しているものが一般的だった。
そのためC言語のクロスコンパイラを用いて、ハンディースキャナーへ転送するのが一般的だった。
メモリー的にも速度的にもC言語(もしくはアセンブラ)を使うのが必須で、開発するにもそれなりにノウハウが必要でハードルが高かったことは間違いないだろう。
一般的なバーコードリーダーでもそんな状態だったため、QRコードはさらに高性能なCPUや周辺機器を必要としていただろう。おそらく当時デンソー社にはQRコード用の製品を販売していたと思うが、製品価格的に高価格帯の車業界以外では普及が難しかったとのでは?と推定している。
ところがである。
それが今ではスマートフォンは誰でも持っている。といことは誰でもハンディースキャナーを潜在的に持っているのだ。しかも機能が足りなければ遠隔でプログラム変更までできてしまう。
開発するにしても当時とは比較にならないほどメモリーもCPUも高速化され、ライブラリーも用意されているから比較的コストをかけずに開発できてしまう。読み取り性能も上がっているはずだ。
二次元コードそのものは何も変わっていないのに、使われ方次第で驚きの進化を遂げた。
当時スマートフォンの登場は全く予想できていなかったが、現在のスマートフォンとの相性は抜群だ。おサイフケータイ等の非接触のICカードリーダーを持たないスマートフォンは多々あるが、特殊な機種を除いてカメラの無いスマートフォンは見かけない。全てのスマートフォンで利用可能なのである。
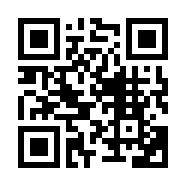
実際に「www.nouno.com」に接続できるQRコードである。こんなことがいとも簡単にできるようになったのは感慨深い。
おそらく現在でも???という技術があっても、もしかしたら20~30年後に花開くかも知れない。基礎技術の大切さを、この歳で知ったのだった。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です




コメント