MS-DOSの時代、フロッピーディスクの1.44MB(PC-9801だと1.25MB)を超えるデータのやりとりをするとなると、一部でMOが普及していた。CD-R装置は存在していたが非常に高価で全く普及はしておらず互換性の問題もあった。
MOはPC-9801用のMS-DOSでも標準サポートされていたのだが、実際は特殊な用途のみで使用されていた。
デザイン関係のデータはデータサイズが大きかったのでフロッピーディスクに収まらないことも多かった。フロッピーディスク数枚に分割して保存することもできたのだが、特殊な方法でお互い面倒なこともあり日本においてはMOでのやりとりが標準だった。ただデザイン関係はMacが標準だったので、PC-9801シリーズに限定すると一部の企業とマニアな方だけに普及していた感じだった。
ほとんどのアプリケーションのユーザーデータは、2000年を過ぎてもフロッピーディスクにギリギリ保存できるデータサイズだった。これより大きいサイズになったのはCD-R装置へのデータ書き込みが普及してからだろう。
読み込みのみのCD-ROMは、ほぼWindows3.1用としてだがMS-DOSからも直接アクセスできた。Windows95は当然ロングファイルネームも利用できたが、MS-DOSからは8.3形式のみ利用可の制限があった。
さらにMS-DOSから利用する場合、CONFIG.SYSと呼ばれるファイルへ自力でデバイスドライバに登録しドライブとして認識させる必要があった。Windows.3.1プリインストールのPCであれば気にする必要も無かったが、後付けとなるとそれなりに知識が必要だった。
Windows95以降に発売されたCD-ROM装置の多くはMS-DOSはサポート対象外だった。サポート対象となるものは旧タイプのもので、そこそこ高価だった。
老兵はWindows95とMS-DOS6.2+Windows3.1のデュアルブートにしていた。後年CD-ROMの代わりにPDと呼ばれる装置に換装したのだが当然サポート外だった。
ただCD-ROM読取の部分はなんとか標準デバイスドライバで対応ができたので、特に使用に問題はなかった。
実際のところWindows95の時代においても、まだまだデータの受け渡しはフロッピーディスクを主に使用していた。書き込みができるCD-R装置は高価で、メディアも高価であり普及はしていなかった。
この頃は肥大化するソフトウェアのインストールが主な用途だったので、特に困ってはいなかった。
読込速度も、等倍、倍速の装置も存在したが、実際に普及し始めたのは4倍速からだろう。
インストール用データも一般的には数十MB程度の量しかなかった。雑誌の付録なんかは最大容量で詰め込んだものもあったが、全部をPCへ転送することは無く、この速度でも全然問題がなかった。インストールやアップデートのためだけなので、一度読み込んだら再度利用することも少なかった。
ただこの頃からCPUのクロック数戦争の裏で、静かにCDの読込速度戦争が発生しており、1999年には72倍速の装置まで存在してた。
ただ高速になるほど音が大きくうるさかった。よって最大読込速度は控えめに静音を目的としたドライブもあった。
またCD-ROMを頻繁に入れ替える方向けに、CD-ROMチェンジャーまで存在した。

Windows95以降のPCはCD-ROM装置は標準搭載となり、Windows98以降になると、より容量の多いDVD-ROMの搭載が始まった。
この頃になると書き込みが出来るCD-R装置の価格も安くなり、一般ユーザーにも徐々に普及していった。
CD-Rの普及は企業においてはデータの受け渡しがメインだったが、一般ユーザーは音楽CDをコピーするためがメインだった。当時はレンタルCDショップが全盛期で、お店にはコピー用のCD-Rメディアが置いてあるのが普通だった。
一般にはあまり知られていないが、CD-Rは一応データ用と音楽用に分かれている。
音楽用CD-Rには「私的録音補償金」が含まれており、特殊な識別コードが設定されている。よって一般的には音楽用にCD-Rの方が高額である。
「録音用CD専用レコーダー」はこの識別コードを認識して、音楽データのコピーが行えるようになっているので、データ用CD-Rを入れると録音ができない。
当時からこの装置を購入するような方は、ほとんど見かけなかった。ほとんどのユーザーはPCからコピーを行った。PCの場合この識別コードは無視されるため、データ用CD-Rでもコピーできてしまうのである。本来であれば著作権的に音楽用CD-Rを使うべきなのだが、無視している方が大半なのが現状だ。もちろんレンタルCDショップでも普通にデータ用CD-Rを販売している。一応、ユーザーは音楽CDはコピーしない前提なのだろう。
大々的に普及したのは、DVD-ROMとCD-R/RWが利用できるコンボドライブの発売からだろう。ちょうど2000年頃である。
まだ家庭用DVDプレイヤーは普及を始めたころで、VHSビデオで鑑賞するのが普通だった。
CPUにマルチメディア命令のMMXが搭載され、クロック周波数が500Mhzを超えたあたりからPCでDVD再生できる性能となった。そうなるとPCで映画を楽しむ機会が増えた。
1999年にヒットした映画「MATRIX」は通常のDVD版に加えて、PCでDVDコンテンツが楽しめるアプリケーションが追加された特別版も用意されていた。この頃はPCでDVDを楽しんでいる方のほうが多かっただろう。
多くのPCはDVD-ROM装置だったため、このコンボドライブへ換装または追加することが多かった。
DVD-ROM専用装置は高速かつ安価だったが、コンボドライブは速度はそこそこに高価だった。この頃はタワー型PCが一般的で5インチベイが1つ余っているPCも多く、交換では無く追加することも多かった。
音楽CDをコピーするにも、2台あるとなにかと便利だった。一般的には音楽CDのデータを一度ハードディスクへイメージ保管し、そのイメージをCDへ書き込む。この手順を飛ばしたオンザフライという手法があり、直接コピーすることでコピー時間を短縮することができた。
コンボドライブを購入すると、一緒にDVD再生ソフトやCD-R書き込みソフト等、バンドルされるソフトが付いてくることが普通だった。
あまりCD-R装置の性能に差が無いので、このバンドルソフトで差別化を図っていた感じだ。
再生ソフトは「PowerDVD」か「WinDVD」、書き込みソフトは「B’s Recorder」が多かった記憶がある。
たとえばDVD再生においてはステレオ再生限定で5.1ch再生ができないなどの機能縮小版だったが、PCで5.1ch再生が必要な方は少なく、これで十分だった。
ちなみに老兵は5.1ch再生でDVDを楽しんでいたのだが、普通にホームシアターセットで楽しんでいたので、やっぱり必要がなかった。
音楽CDについては通常ディスクコピー専用のメニューがあったので簡単だったが、PCのデータを保存するとなると書込データのマスターを作るなど、初心者には少々難しかった。
しかも当時は書き込みエラーが頻発していたため、ベリファイ(ちゃんと書き込めているかチェックする)が必須だった。
今では標準搭載され気にもならないが、CD-R装置にバッファーが搭載されていなかった。
書き込みの間、データが適切に流れ続けないと書き込むデータが無くなってしまい途中で失敗してしまうのだ。バッファアンダーランと呼ばれ恐れられた。これを防止するには先読みしてある程度書き込みデータを保存しておけば良いのだが、当時は技術的にもコスト的にも難しかった。後年CD-R装置に少量のバッファーが搭載されただけでニュースになったものだ。
そのため書き込み中のPC操作は厳禁だった。単に触らなければ良いかと思えばスクリーンセーバーが起動すると、そこでエラーになってしまうのである。
スクリーンセーバーのOFFも必須だ。そうそうメールの受信もディスクに書き込みが発生するため終了が基本だ。本当に書き込みソフトだけを起動した。
書込速度は年々上がっており現在では52倍速まである。当時も16倍速などあったのだが、書込速度が速いほどバッファアンダーランが発生する確率が高かったため、結局4倍速で書き込むのが一般的だった。
もちろん、それより遅い速度で書き込めば良いのだが、そうすると今度はCD-Rメディアの関係で遅すぎると焼き込みが強すぎてしまい、別のPCで読み込めない現象が発生した。
高速で書き込みのできる格安のメディアでも4倍速が基も安定的で、暗黙の了解として4倍速書き込みが流行した。
ちなみに重要なデータを書き込むときは「太陽誘電製のCD-R」が最も安定していた。少々高価だったが好んで使用されたものだ。4倍速書き込みであれば本当にエラー頻度が少なく経年劣化にも強かった。名も知れないCD-Rメディアは、安いだけでベリファイで失敗する頻度が異常だし、気がつくと読めなくなっていることも多かった。50枚入りのスピンドルで10枚連続失敗とか普通だったので、結局有名メーカのものを使用した方が安上がりだった。
ちなみに太陽誘電は2025年に光記録メディア事業から撤退している。
尚、現在においては4倍速で書込ができないのが一般的だ。遅すぎてドライブが対応していないのである。指定しても自動で16倍速くらいになってしまうのだ。メディアもそれに合わせている。
2000年を過ぎると企業であれば数MB程度なら電子メールで送信し、それより大きい場合はCD-Rで書き込んで郵送ということが一般的となった。
まだPCにフロッピーディスクは搭載されていたが、ほとんど利用されることが無くなっていった。
こうして、CD-R装置はPCへの搭載と使用は当たり前になっていった。

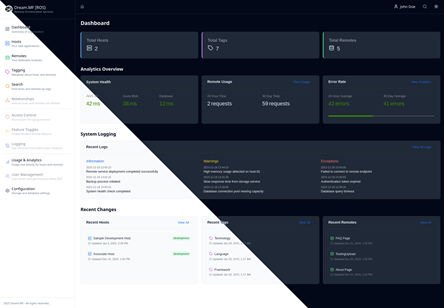

コメント